トラネキサム酸には「肝斑」「そばかす」「炎症後色素沈着」など
しみのもとであるメラニン色素や炎症を抑える効果があります
トラネキサム酸とは?
トラネキサム酸は、合成されたアミノ酸のひとつです。主に炎症の改善に使われることが多く止血や喉の腫れ、口内炎などのアレルギー治療に使用されるほか、肌荒れやシミ、肝斑の改善効もあり厚生労働省が承認しています。
トラネキサム酸の美白効果
トラネキサム酸は美白効果が認められています。これはひとつにトラネキサム酸がプラスミンの働きを抑え、メラニンの生成を阻害することで、肌の色素沈着を防ぐためです。シミや肝斑が生じるのを防止するだけでなく、すでにできているシミや肝斑、そばかす、ニキビ跡による色素沈着も薄くします。トラネキサム酸の定期的に服用すると、肌に透明感がでて1トーン明るくなり、若々しい肌を保つことができるでしょう。
トラネキサム酸の作用機序
トラネキサム酸は、抗出血・抗アレルギー・抗炎症作用にも有効性が認められ、喉の腫れや口内炎を治療する薬、歯磨き粉などに使用されています。またメラニンをつくり出すメラノサイトに働きかけ、色素沈着抑制効果を発揮して肝斑を改善します。
止血作用
トラネキサム酸は、血液を溶かし出血を促す酵素プラスミンを抑制するため、優れた止血作用を発揮します。その止血作用に期待し、全身性線溶亢進が関与すると考えられる出血傾向(白血病、再生不良性貧血、紫斑病等、および処置中・処置後の異常出血)や局所線溶亢進が関与すると考えられる異常出血(肺出血、鼻出血、性器出血、腎出血、及び処置中・処置後の異常出血)などに対して主に使用されます。さらには、外傷性出血患者の死亡リスク低減にも役立った事例があるようです。
抗アレルギー・抗炎症作用
プラスミンはたんぱく質を分解するプロセスで、気炎性ペプチドであるキニンを産出しアレルギーや腫れ・炎症の発現を促すことがわかっています。よって、抗プラスミン物質であるトラネキサム酸には、抗アレルギー・抗炎症作用が期待できます。湿疹及びその類症、蕁麻疹、薬疹・中毒疹における紅斑・腫脹・そう痒等の症状、または、扁桃炎、咽喉頭炎における咽頭痛・発赤・充血・腫脹等の症状が主な適応症です。さらに、口内炎および歯肉炎における口内粘膜アフタにも使用され、歯磨き粉の有効成分に含まれているケースも珍しくありません。
メラニン生成抑制(シミ改善)作用
人間の表皮の9割以上を占めるのが、ケラチノサイトという表皮細胞です。ケラチノサイトは刺激誘引物質である紫外線や女性ホルモンの影響を受けると、先述したプラスミン、あるいはプロスタグランジンといったメラノサイト活性化因子(情報伝達物質)を産出してしまいます。メラノサイトとは、表皮の最下層である基底層に存在する色素細胞です。
情報伝達物質のシグナルを受け取ったメラノサイト内では、チロシンというアミノ酸が徐々にシミの元であるメラニンに変化し、周囲のケラチノサイトへ次々と受け渡されていきます。メラニン自体は、紫外線を吸収し肌細胞をダメージから守る役割があり、人間にとってプラスの一面があるのは確かです。しかし、生成されたメラニンがケラチノサイトに過剰に溜まっていくと、メラニン色素が肌に沈着してついにはシミや肝斑ができあがってしまいます。
そこで注目されるのが、抗プラスミン物質として知られるトラネキサム酸です。トラネキサム酸には、メラニンを生成する色素細胞メラノサイトの活性化因子(プラスミンやプロスタグランジン)を阻害する作用があります。この働きにより、メラノサイトは「メラニンを作ろう」というシグナルそのものを受信できず、メラニンの生成プロセスは早い段階でトラネキサム酸にブロックされてしまうのです。また、色素沈着が起きてシミがある部位に関しても、メラノサイトの活性化が継続的に抑えられ抗炎症作用も加わることで、美白効果が期待できます。
副作用や注意点について
トラネキサム酸は基本的に副作用が起きる確率は低く、安全性の高い薬品と認識されています。仮に適応症に該当しない人が服用したとしても、身体に悪影響が出るような成分ではありません(実際の服用に際しては、使用上の注意を読んで正しく服用するのは大前提です)。その一方、薬品である以上は、副作用などが起こる可能性はゼロとは言い切れず、一定の関連情報は把握しておいた方がいいでしょう。稀なケースではありますが、皮膚の痒み、発疹、食欲不振、悪心、嘔吐、下痢、胸やけ、眠気などが起こりうる副作用として想定されます。人工透析の患者に痙攣があらわれる可能性という報告もあるので該当する場合は注意が必要です。なお、トラネキサム酸の内服は効果が出るまで時間を要するため、自身の体調は気長に構えて様子を見る必要があります。
トラネキサム酸は止血作用に優れている分、血栓に関わる病気である脳梗塞・狭心症、心筋梗塞・血栓性静脈炎・消費性凝固障害などのある人、術後の臥床状態にある患者及び圧迫止血の処置を受けている患者、腎不全の患者であれば、慎重に服用すべきです。薬の飲み合わせとしては、同じく止血剤として使用されるトロンビンとは併用できません。双方の成分が合わさることで、血栓ができやすくなってしまうからです。トロンビンは特に胃の止血のために処方されるケースが多く、トラブルを防ぐためにも診察時には服用中の薬を確実に伝える姿勢が大切です。さらに、副作用で血栓症のおそれがあるピル(経口避妊薬)ですが、トラネキサム酸との併用で血栓症リスク上昇が疑われるという見方もあるため、同時服用の際はよく医師に相談しましょう。
女性ホルモンに対する影響の有無
シミの中でも特に肝斑については、紫外線だけでなく女性ホルモンの影響が大きいと言われています。そこで、肝斑の処方薬として代表的なトラネキサム酸が、女性ホルモンに対して作用するのか気になる人がいるかもしれません。既述のように、トラネキサム酸の作用メカニズムは、メラノサイト活性化因子の抑制です。よって、肝斑改善のために、女性ホルモンへ働きかけているわけではありません。実際の研究成果を踏まえても、トラネキサム酸は女性ホルモン分泌へ直接影響を及ぼさないと見られています。
トラネキサム酸によるシミ対策とは
トラネキサム酸とは、人工的に生成されたアミノ酸の一種でシミや肝斑の治療にも使われます。トラネキサム酸には、シミの元になるメラノサイトの活性化を抑える効果が期待できます。トラネキサム酸によるシミ対策には、医薬品として内服する方法と成分が含まれている化粧品を使用する方法があります。
詳細情報
| 効果 | 皮膚のしみを薄くする効果があります。止血作用のある薬ですが、炎症を抑える作用もあり、それによりシミが薄くなります。 |
|---|---|
| 用法 | 毎食後に内服1日3回(1回1カプセル)
|
取扱い上の注意
- 副作用
主な副作用として、かゆみ、発疹、食欲不振、吐き気、嘔吐、胸やけなどが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。
上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。 - 注意点
脳梗塞・狭心症、心筋梗塞・腎不全・血症性静脈炎などの既往症、もしくはそれらのリスクがあると診断されている方は服用できません。
市販薬と医薬品の違い
同じ成分が含まれているものでも、市販薬として出されているものもあれば医療用医薬品として扱われている場合もあります。では、市販薬と医療用医薬品とはどのような違いがあるのか説明していきます。
市販薬とは?
市販薬とは、医療用医薬品よりも主成分の含有量が少なく設定されているもので、「一般用医薬品」のことです。市販薬は、医師の処方箋がなくても手に入ることから、家庭薬や大衆薬とも呼ばれています。また、カウンター越しで購入できるという意味(Over The Counter)を持つOTC医薬品も市販薬の呼び名の一つです。いずれにしても、自分の判断で購入できる薬品と考えればいいでしょう。厚生労働省のホームページを見ると、一般医薬品として「第1類医薬品」と「第2類医薬品」、そして「第3類医薬品」の3つに分類しています。
医療用医薬品とは?
医療用医薬品とは、病院など医療機関で医師による診断を受け、処方箋を発行してもらったうえで購入できる医薬品のことです。市販薬に比べると成分の含有量が高い傾向がある反面、副作用にも注意を必要とするものが多く、処方箋をもとに薬剤師が調剤しなければなりません。ただし、患者の症状に合った薬品を処方されるため、その分症状の緩和や治療に適した医薬品が多いといえます。
1日の上限量
トラネキサム酸の1日あたりの上限量は、医療用医薬品の場合は2,000mgに対して市販薬は750mgと定められています。トラネキサム酸の高い効果を得るためには、市販薬よりも2倍以上の成分が含有されている医療用医薬品を推奨します。ただし医療用医薬品のトラネキサム酸は、医療機関で受診をし医師の判断のもと正しく服用してください。
トラネキサム酸のドクターコメント
よくあるご質問 Q&A
- Q 市販薬のトラネキサム酸と、医療機関の処方薬の違いは何ですか?
-
A
市販薬と医療機関で処方される医薬品の違いは主成分の含有量にあります。トラネキサム酸の場合も同様で、医療用医薬品の方が市販薬より含有量が多くなっています。そのため、通常、市販薬はトラネキサム酸だけが含有されていることはありません。皮膚のターンオーバーを促進したりメラニンの生産量を抑制したりといったことを目的とした他の成分も一緒に含まれているのが一般的です。一緒に含有されている成分は、例えば、L-システインやビタミンCなどがあげられます。
これに対して、医療機関で処方される医薬品の多くはトラネキサム酸だけが含有されています。実際に肌の状態を診断してから処方されるため、自分の症状に合ったシミの治療が可能になります。そのため、シミ治療にしっかり取り組んでいくなら医師に診断してもらい、自分の肌質やシミの状態に合った処方薬を使う方がいいでしょう。 - Q トラネキサム酸に副作用はありますか?
-
A
トラネキサム酸には、いくつかの副作用があることがわかっています。副作用として起こり得るものは、食欲不振や嘔吐、下痢、胸やけ、悪心などです。他にも眠気をもよおすこともありますし、湿疹や痒みなど皮膚への影響が見られることもあります。人工透析患者において痙攣発生の可能性があるともされています。また、トラネキサム酸はプラスミンの機能が強まることによる大量出血の治療で止血に使われます。よって、心筋梗塞や脳梗塞、狭心症、血栓性静脈炎のような血栓性の病気を持つ人、消費性凝固障害のある人は、服用について十分注意をはらう方がいいでしょう。
他にも術後の臥床状態にある人や圧迫止血の処置を受けている人、腎不全の人などにも慎重に投与することが求められています。トラネキサム酸は、医薬品だけでなく歯磨き粉にも含まれているなど安全性が高い成分として認知されてはいますが、気になることがある人は医師に相談のうえで処方を受けることが大切といえます。 - Q トラネキサム酸は、クリニックに行かないと処方してもらえませんか?
-
A
トラネキサム酸は、市販薬としても販売されています。ドラッグストアのような量販店や薬局などでも購入できますし、オンラインでの入手も可能です。内服薬として服用するものから、気になる部分に直接塗布できるクリームや美白美容液までさまざまなタイプが出ています。しかし、市販薬として購入できるのは、トラネキサム酸の含有量が少ないものに限定されています。
シミの治療薬としてトラネキサム酸を使いたいときは、クリニックなどで医師に診断してもらう方がいいでしょう。肌やシミの状態をきちんと診てもらったうえで処方してもらう方が、自分に合った治療につながります。また、血栓性の病気で治療を受けたばかりの人などは、クリニックなら医師に相談したうえでシミの治療を検討することもできるでしょう。色素沈着やシミ、肝斑で悩んでいるなら、クリニックでトラネキサム酸を処方してもらった方が適切な改善が期待できます。
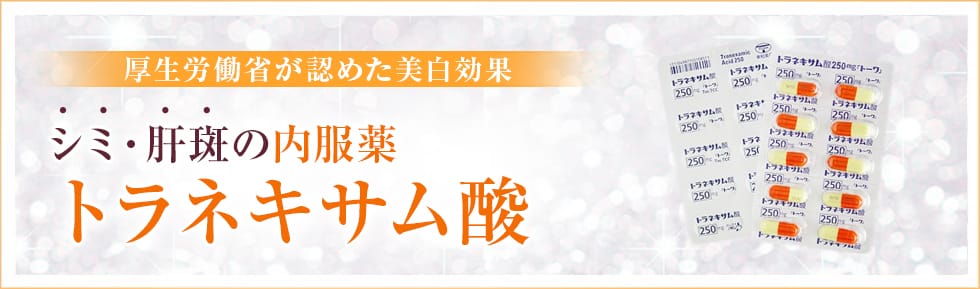
 2,120
2,120

トラネキサム酸は、美白を目指す方に注目されている成分で、肌全体のトーンアップや透明感を高める効果が期待できます。特に肝斑や色素沈着の改善に効果的とされており、内服や外用薬、点滴療法として取り入れられることが多いです。
内服の場合、内側から作用することで肌トラブルをケアし、外用薬や点滴療法では、肌表面からのアプローチでトータルな美白ケアをサポートします。治療を続けることで、シミや肝斑の目立たない透明感のあるお肌を目指すことが可能です。
ただし、妊娠中・授乳中の方や血栓症のリスクがある方は、使用が制限される場合がありますので、治療の前に医師にご相談ください。
品川スキンクリニック 横浜院院長 方波見 有貴
品川スキンクリニック 横浜院
院長 方波見 有貴